Script(Japanese)
*If you want to see Hiragana please watch my YouTube
みなさんこんにちは、みきこです。
私のPodcastを聞いてくれてありがとうございます。
インドネシアで市場に行くと、鶏肉が姿のまま売られていたり、魚も姿のままや、生きたままのものが売られていることもあります。
みなさんの国ではどうですか?
日本に住んでいるとなかなか姿をみることはありません。
肉も魚も切り身で売られています。
ですので日本に住んでいると「命をいただいている」という感覚が起きにくいです。
ですので、「いただきます」と「ごちそうさま」の言葉はとても大切だなと思っています。
今日は、普段何気なく使っている「いただきます」と「ごちそうさま」に関する深い話をしようと思います。
まず、「いただきます」についてです。
「いただきます」には2つの意味があるんですよ。
食事をする前に、日本人は必ず「いただきます」と言いますよね。
これには、どんな意味があるのでしょうか?
「いただきます」という言葉は、もともと「いただく」という謙譲語(けんじょうご)から来ています。
「いただく」は「もらう」の丁寧な言い方です。
ですから、「いただきます」は「命(いのち)をもらいます」という意味になるんです。
どういうことかと言うと、食べ物には、私たちが生きるための「命」が含まれています。
たとえば、お米や野菜は植物の命ですし、お肉や魚は動物の命ですね。
「いただきます」という言葉を使うことで、「その命に感謝します」という気持ちを表しているんです。
それからもう一つ「いただきます」には意味があって、それは作ってくれた人への感謝の気持ちです。
単に料理を作ってくれた人にだけではなく、食材を育ててくれた人や食卓に運んでくれた人など、食事に携わる全ての人への感謝の気持ちも表しています。
ですので自分で作った場合でも、「いただきます」と言いますし、それはとても自然なことです。
「いただきます」は、命を”いただく”ことに対しての感謝の気持ちと、作ってくれた人への感謝の気持ちを表しているんです。
はい、次に「ごちそうさま」についてお話をします。
食事が終わった後、日本人は「ごちそうさま」と言いますよね。
これも、ただの習慣ではなく、大切な意味があります。
「ごちそうさま」は漢字にしてみると「ご馳走様」とこのように書きます。
「馳」も「走」もどちらも「走る」という意味の漢字で、食事を作る為に走り回る様子を表しています。
昔の日本では、食材を集めるために、人々があちこち走り回りました。
今の時代とは違って、食材を保存する冷蔵庫がなかったので、食材を集めに走り回っていました。
その努力のおかげで、美味しい食事を楽しむことができたんです。
「ごちそうさま」は、その努力に対する感謝の気持ちを表す言葉なんです。
さらに、「ごちそうさま」には、一緒に食事をした人や料理を作ってくれた人への感謝も込められています。
たとえば、友達や家族と一緒に食べたとき、「ごちそうさま」と言うことで、その楽しい時間を共有できたことにも感謝を伝えられるんです。
「いただきます」と「ごちそうさま」は、日本人の感謝の気持ちを表す素敵な言葉です。
そして、これらの言葉には、他にも日本の文化が反映されています。
たとえば、「自然との調和(ちょうわ)」です。
日本では、古くから自然を大切にする文化があります。
食べ物の命に感謝することで、自然とのつながりを意識することができます。
また、「人とのつながり」も重要なポイントです。
料理を作る人、食材を育てる人、そして一緒に食事をする人、すべてに感謝をすることで、人々のつながりを深めることができます。
「いただきます」と「ごちそうさま」のような言葉はみなさんの国にもあるんじゃないかなと思います。
そこにはどんな意味が込められていますか?
はい、ということで今日はここまでです。
「いただきます」と「ごちそうさま」は、ただの言葉ではありません。
それぞれの言葉には、命や努力、そして人々への感謝が込められています。
この2つの言葉を大切にすることで、日本の文化や価値観をより深く理解することができると思います。
みなさんも使う時はこの意味を思い出して使ってみてくださいね。
最後まで聞いてくれてありがとうございました。
ほなまたね!(じゃあまたね)
Contact Form
質問や仕事の依頼など問い合わせはこちらからどうぞ。
Feel free to send any questions or job requests through this form.

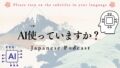
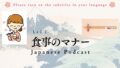
コメント